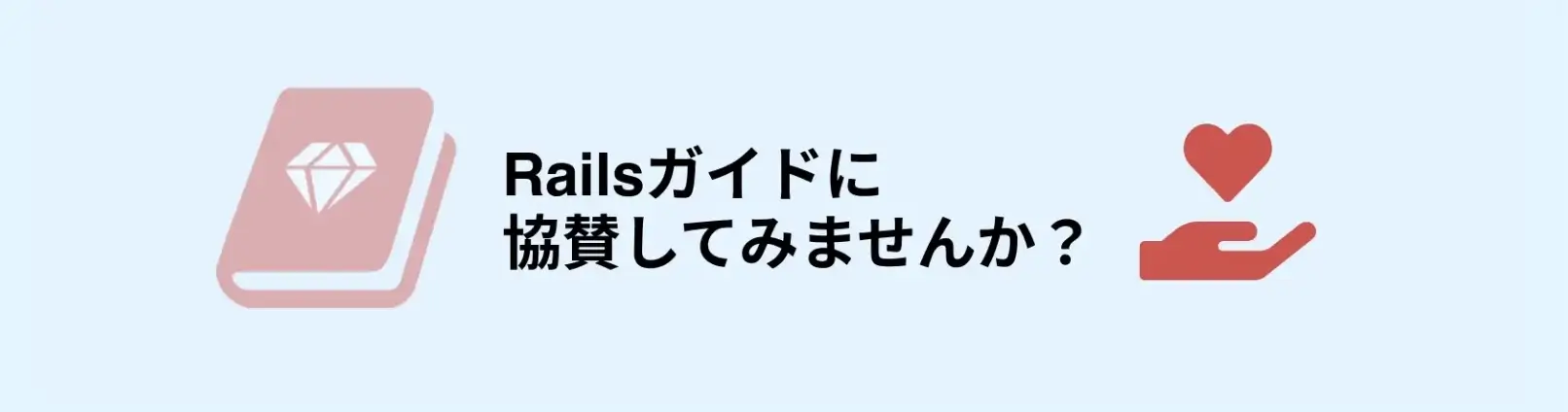Railsのコマンドラインは、Ruby on Railsフレームワークの強力な機能の一部です。Railsの規約に沿った定型コードを生成することで、新しいアプリケーションを短時間で構築できます。本ガイドでは、データベースを含むWebアプリケーションのあらゆる側面を管理できるさまざまなRailsコマンドの概要を説明します。
bin/rails --helpと入力すると、利用可能なコマンドの一覧が表示されます。表示されるコマンドは、現在のディレクトリに応じて変わります。コマンドごとに、その機能の説明が表示されます。
$ bin/rails --help
Usage:
bin/rails COMMAND [options]
You must specify a command. The most common commands are:
generate Generate new code (short-cut alias: "g")
console Start the Rails console (short-cut alias: "c")
server Start the Rails server (short-cut alias: "s")
test Run tests except system tests (short-cut alias: "t")
test:system Run system tests
dbconsole Start a console for the database specified in config/database.yml
(short-cut alias: "db")
plugin new Create a new Rails railtie or engine
All commands can be run with -h (or --help) for more information.
bin/rails --helpの出力では、上に続いてすべてのコマンドがアルファベット順に表示され、それぞれのコマンドに簡単な説明が表示されます。
In addition to those commands, there are:
about List versions of all Rails frameworks ...
action_mailbox:ingress:exim Relay an inbound email from Exim to ...
action_mailbox:ingress:postfix Relay an inbound email from Postfix ...
action_mailbox:ingress:qmail Relay an inbound email from Qmail to ...
action_mailbox:install Install Action Mailbox and its ...
...
db:fixtures:load Load fixtures into the ...
db:migrate Migrate the database ...
db:migrate:status Display status of migrations
db:rollback Roll the schema back to ...
...
turbo:install Install Turbo into the app
turbo:install:bun Install Turbo into the app with bun
turbo:install:importmap Install Turbo into the app with asset ...
turbo:install:node Install Turbo into the app with webpacker
turbo:install:redis Switch on Redis and use it in development
version Show the Rails version
yarn:install Install all JavaScript dependencies as ...
zeitwerk:check Check project structure for Zeitwerk ...
bin/rails --help に加えて、上記のリストにあるコマンドに--helpフラグを追加して実行するのも便利です。たとえば、bin/rails routesコマンドでどんなオプションが使えるかを知りたいときは、以下のようにbin/rails routes --helpを実行します。
$ bin/rails routes --help
Usage:
bin/rails routes
Options:
-c, [--controller=CONTROLLER] # Filter by a specific controller, e.g. PostsController or Admin::PostsController.
-g, [--grep=GREP] # Grep routes by a specific pattern.
-E, [--expanded], [--no-expanded] # Print routes expanded vertically with parts explained.
-u, [--unused], [--no-unused] # Print unused routes.
List all the defined routes
Railsのコマンドラインのほとんどのサブコマンドは--help(または -h)フラグ付きで実行可能で、サブコマンドの利用方法が非常に詳しく表示されます。たとえばbin/rails generate model --helpを実行すると、利用方法とオプションに加えて、2ページにわたる詳しい説明が出力されます。
$ bin/rails generate model --help
Usage:
bin/rails generate model NAME [field[:type][:index] field[:type][:index]] [options]
Options:
...
Description:
Generates a new model. Pass the model name, either CamelCased or
under_scored, and an optional list of attribute pairs as arguments.
Attribute pairs are field:type arguments specifying the
model's attributes. Timestamps are added by default, so you don't have to
specify them by hand as 'created_at:datetime updated_at:datetime'.
As a special case, specifying 'password:digest' will generate a
password_digest field of string type, and configure your generated model and
tests for use with Active Model has_secure_password (assuming the default ORM and test framework are being used).
...
以下は、利用頻度の高いRailsコマンドです。
bin/rails consolebin/rails serverbin/rails testbin/rails generatebin/rails db:migratebin/rails db:createbin/rails routesbin/rails dbconsolerails new app_name
以下のセクションでは、上を含むさまざまなコマンドについて説明します。
最初は、新しいアプリケーションを作成するためのコマンドです。
rails newコマンドを実行すると、新しいRailsアプリケーションが作成されます。
rails newコマンドを実行するには、事前にrails gemをインストールしておく必要があります。Rubyの使える環境であればgem install railsを実行することでインストールできます。詳しい手順については、Ruby on Railsインストールガイドガイドを参照してください。
newコマンドを実行すると、Railsで必要なデフォルトのディレクトリ構造全体と、サンプルアプリケーションをすぐに実行するために必要なすべてのコードがセットアップされます。rails newの第1引数にはアプリケーション名を指定します。
$ rails new my_app
create
create README.md
create Rakefile
create config.ru
create .gitignore
create Gemfile
create app
...
create tmp/cache
...
run bundle install
newコマンドにさまざまなオプションを渡すことで、デフォルトの動作を変更できます。
また、独自のアプリケーションテンプレートを作成しておいてnewコマンドで利用することも可能です。
rails newコマンドで新しいRailsアプリケーションを作成するときに、アプリケーションで使うデータベースを--database(または-d)オプションで指定できます。rails newのデフォルトデータベースはSQLiteです。たとえば、PostgreSQLデータベースは次のように設定できます。
$ rails new booknotes --database=postgresql
create
create app/controllers
create app/helpers
...
このオプションを指定したときの主な違いは、config/database.ymlファイルの内容です。PostgreSQLオプションを指定した場合、config/database.ymlファイルは以下のようになります。
# PostgreSQL. Versions 9.3 and up are supported.
#
# Install the pg driver:
# gem install pg
# On macOS with Homebrew:
# gem install pg -- --with-pg-config=/usr/local/bin/pg_config
# On Windows:
# gem install pg
# Choose the win32 build.
# Install PostgreSQL and put its /bin directory on your path.
#
# Configure Using Gemfile
# gem "pg"
#
default: &default
adapter: postgresql
encoding: unicode
# For details on connection pooling, see Rails configuration guide
# https://guides.rubyonrails.org/configuring.html#database-pooling
pool: <%= ENV.fetch("RAILS_MAX_THREADS") { 3 } %>
development:
<<: *default
database: booknotes_development
...
--database=postgresqlオプションを指定すると、新しいRailsアプリケーションで生成される他のファイルもそれに応じて適切に変更されます(Gemfileにpg gemを追加するなど)。
rails newコマンドを実行すると、多数のファイルが生成されます。
生成したくないファイルがある場合は、以下のようにrails newコマンドに--skipオプションを追加することで生成をスキップできます。
$ rails new no_storage --skip-active-storage
Based on the specified options, the following options will also be activated:
--skip-action-mailbox [due to --skip-active-storage]
--skip-action-text [due to --skip-active-storage]
create
create README.md
...
上の例では、Active Storageがスキップされるのに加えて、Active Storage機能に依存しているAction MailboxとAction Textもスキップされます。
--skipオプションでスキップできる機能の完全なリストは、rails new --helpコマンドで確認できます。
bin/rails serverコマンドを実行すると、PumaというWebサーバーが起動します(PumaはRailsに標準でバンドルされます)。Webブラウザでアプリケーションにアクセスしたいときは、このコマンドを使います。
$ cd my_app
$ bin/rails server
=> Booting Puma
=> Rails 8.1.0 application starting in development
=> Run `bin/rails server --help` for more startup options
Puma starting in single mode...
* Puma version: 6.4.0 (ruby 3.1.3-p185) ("The Eagle of Durango")
* Min threads: 3
* Max threads: 3
* Environment: development
* PID: 5295
* Listening on http://127.0.0.1:3000
* Listening on http://[::1]:3000
Use Ctrl-C to stop
わずか2つのコマンドを実行しただけで、Railsサーバーを3000番ポートで起動できるようになりました。ブラウザを立ち上げて、http://localhost:3000を開いてみてください。Railsアプリケーションが動作していることが分かります。
ほとんどのRailsコマンドには短縮形のエイリアスがあります。サーバーを起動する際にはbin/rails sのように"s"というエイリアスが使えます。
-
-pオプションでリッスンするポートを変更できます。
-
-eオプションでサーバーの環境を変更できます。デフォルトではdevelopment(開発)環境で実行されます。
$ bin/rails server -e production -p 4000
-
-bオプションで、Railsを特定のIPアドレスにバインドできます。デフォルトはlocalhostです。
-
-dオプションを指定すると、起動したサーバーがデーモンとして常駐します。
bin/rails generateコマンドを実行すると、さまざまなファイルを生成してアプリケーションに機能を追加できます。モデルのファイルやコントローラのファイルを生成したり、scaffoldですべてのファイルを一括生成したりできます。
Rails組み込みのジェネレータの一覧を見るには、引数なしでbin/rails generate(または短縮形のbin/rails g)を実行します。利用法に続けて、利用可能なジェネレータがすべて表示されます。特定のジェネレータを実行せずにどんなファイルが生成されるかだけを知りたい場合は、--pretendオプションを指定できます。
$ bin/rails generate
Usage:
bin/rails generate GENERATOR [args] [options]
General options:
-h, [--help] # Print generator's options and usage
-p, [--pretend] # Run but do not make any changes
-f, [--force] # Overwrite files that already exist
-s, [--skip] # Skip files that already exist
-q, [--quiet] # Suppress status output
Please choose a generator below.
Rails:
application_record
benchmark
channel
controller
generator
helper
...
Railsアプリケーションにgemを追加すると、ジェネレータが追加される場合があります。また、ジェネレータを自作することも可能です。詳しくはジェネレータのガイドを参照してください。
ジェネレータを使うと、アプリケーションを動かすのに必要なボイラープレートコード(定形コード)を書かなくて済むため、多くの時間を節約できます。
それではcontrollerジェネレータを使って、コントローラを作ってみましょう。
bin/rails generate controllerコマンドだけを実行すれば、--helpオプションを付けて実行したときと同じように、controllerジェネレータの詳しい利用法を表示できます。"Usage"セクションとコマンド例が表示されます。
$ bin/rails generate controller
Usage:
bin/rails generate controller NAME [action action] [options]
...
Examples:
`bin/rails generate controller credit_cards open debit credit close`
This generates a `CreditCardsController` with routes like /credit_cards/debit.
Controller: app/controllers/credit_cards_controller.rb
Test: test/controllers/credit_cards_controller_test.rb
Views: app/views/credit_cards/debit.html.erb [...]
Helper: app/helpers/credit_cards_helper.rb
`bin/rails generate controller users index --skip-routes`
This generates a `UsersController` with an index action and no routes.
`bin/rails generate controller admin/dashboard --parent=admin_controller`
This generates a `Admin::DashboardController` with an `AdminController` parent class.
コントローラのジェネレータにはgenerate controller コントローラ名 アクション1 アクション2という形式でパラメータを渡します。helloアクションを実行すると、ちょっとしたメッセージを表示するGreetingsコントローラを作ってみましょう。
$ bin/rails generate controller Greetings hello
create app/controllers/greetings_controller.rb
route get 'greetings/hello'
invoke erb
create app/views/greetings
create app/views/greetings/hello.html.erb
invoke test_unit
create test/controllers/greetings_controller_test.rb
invoke helper
create app/helpers/greetings_helper.rb
invoke test_unit
コマンドを実行すると、アプリケーションでさまざまなディレクトリが作成され、コントローラファイル、ビューファイル、機能テストのファイル、ビューヘルパーファイルなどが生成され、ルーティングも追加されます。
生成されたコントローラ(app/controllers/greetings_controller.rb)とビュー(app/views/greetings/hello.html.erb)をエディタで開いて、helloアクションを以下のように変更してみましょう。
class GreetingsController < ApplicationController
def hello
@message = "こんにちは、ご機嫌いかがですか?"
end
end
<h1>ごあいさつ</h1>
<p><%= @message %></p>
bin/rails serverでサーバーを起動します。
$ bin/rails server
=> Booting Puma...
bin/rails serverコマンドを実行してRailsサーバーを起動し、追加したルーティングをブラウザでhttp://localhost:3000/greetings/helloにアクセスすると、先ほど追加したメッセージが表示されます。
次は、ジェネレータを使ってアプリケーションにモデルを追加してみましょう。
Railsのモデルジェネレータコマンドにも、非常に詳細な「Description(説明)」セクションが用意されています(以下は冒頭のみを表示しています)。
$ bin/rails generate model
Usage:
bin/rails generate model NAME [field[:type][:index] field[:type][:index]] [options]
...
たとえば、postモデルを生成するには以下のようにコマンドを実行します。
$ bin/rails generate model post title:string body:text
invoke active_record
create db/migrate/20250807202154_create_posts.rb
create app/models/post.rb
invoke test_unit
create test/models/post_test.rb
create test/fixtures/posts.yml
モデルのジェネレータを実行すると、テストファイルやマイグレーションファイルも生成されます。生成後にbin/rails db:migrateコマンドでマイグレーションを実行する必要があります。
Railでは、コントローラやモデルを個別に生成するジェネレータの他に、標準的なCRUDリソースに必要な他のファイルとともに両方のコードを一度に追加するジェネレータも提供しています。これを行うジェネレータコマンドは、resourceコマンドとscaffoldコマンドの2つです。
resourceコマンドは、後述するscaffoldコマンドよりも軽量で、生成されるコードが少なくなります。
bin/rails generate resourceコマンドを実行すると、「モデル」「マイグレーション」「空のコントローラ」「テスト」ファイルが生成され、ルーティングが追加されます。ビューは生成されず、コントローラにCRUDメソッドも追加されません。
以下は、resourceコマンドでpostリソースを生成したときの全ファイルです。
$ bin/rails generate resource post title:string body:text
invoke active_record
create db/migrate/20250919150856_create_posts.rb
create app/models/post.rb
invoke test_unit
create test/models/post_test.rb
create test/fixtures/posts.yml
invoke controller
create app/controllers/posts_controller.rb
invoke erb
create app/views/posts
invoke test_unit
create test/controllers/posts_controller_test.rb
invoke helper
create app/helpers/posts_helper.rb
invoke test_unit
invoke resource_route
route resources :posts
resourceコマンドは、ビューが不要な場合(APIを書く場合など)や、コントローラのアクションを手動で追加したい場合に使います。
Railsのscaffold(足場)は、リソースのための完全なファイルセットを生成します。これには、「モデル」「コントローラ」「ビュー(HTMLおよびJSON)」「マイグレーション」「テスト」「ヘルパー」のファイルが含まれ、ルーティングも追加されます。
scaffoldは、CRUDインターフェイスのプロトタイピングを迅速に実行したいときや、カスタマイズ可能なリソースの基本構造を生成するための出発点として利用できます。
postリソースをscaffoldコマンドで生成すると、上記のすべてのファイルが生成されることを確認できます。
$ bin/rails generate scaffold post title:string body:text
invoke active_record
create db/migrate/20250919150748_create_posts.rb
create app/models/post.rb
invoke test_unit
create test/models/post_test.rb
create test/fixtures/posts.yml
invoke resource_route
route resources :posts
invoke scaffold_controller
create app/controllers/posts_controller.rb
invoke erb
create app/views/posts
create app/views/posts/index.html.erb
create app/views/posts/edit.html.erb
create app/views/posts/show.html.erb
create app/views/posts/new.html.erb
create app/views/posts/_form.html.erb
create app/views/posts/_post.html.erb
invoke resource_route
invoke test_unit
create test/controllers/posts_controller_test.rb
create test/system/posts_test.rb
invoke helper
create app/helpers/posts_helper.rb
invoke test_unit
invoke jbuilder
create app/views/posts/index.json.jbuilder
create app/views/posts/show.json.jbuilder
create app/views/posts/_post.json.jbuilder
Rails 8.1から、scaffoldはデフォルトでシステムテストを生成しなくなりました。システムテストは実行に時間がかかり、メンテナンスコストも高いため、利用は重要なユーザーパスに限定すべきです。scaffoldでシステムテストを含めるには、--system-tests=trueオプションを指定します。
この時点で、bin/rails db:migrateを実行してpostテーブルを作成できます(このコマンドについて詳しくはデータベースを管理するを参照してください)。
終わったらbin/rails serverコマンドでRailsサーバーを起動し、http://localhost:3000/postsにアクセスすると、postリソースで投稿の一覧表示、新規投稿の作成、編集および削除が可能になります。
scaffoldで生成されるテストファイルにはテストケースが含まれていないため、コードを修正して実際にテストケースを追加する必要があります。コードのテストの作成と実行について詳しくは、テスティングガイドを参照してください。
generatorコマンドでモデルやコントローラやscaffoldなどを生成するときに入力を間違えると、ジェネレータで作成された各ファイルを手動で削除するのは面倒です。Railsにはそのためのdestroyコマンドが用意されています。destroyはgenerateの逆の操作とみなすことが可能で、generateが行ったことを調べて、それを取り消します。
destroyコマンドを実行するときにbin/rails dのように"d"というエイリアスも使えます。
たとえば、articleモデルを生成するときに間違えてartcleと入力してしまった場合を考えてみましょう。
$ bin/rails generate model Artcle title:string body:text
invoke active_record
create db/migrate/20250808142940_create_artcles.rb
create app/models/artcle.rb
invoke test_unit
create test/models/artcle_test.rb
create test/fixtures/artcles.yml
こんなときは、generateコマンドで生成された内容をdestroyコマンドで取り消せます。
$ bin/rails destroy model Artcle title:string body:text
invoke active_record
remove db/migrate/20250808142940_create_artcles.rb
remove app/models/artcle.rb
invoke test_unit
remove test/models/artcle_test.rb
remove test/fixtures/artcles.yml
bin/rails consoleコマンドを実行すると、Railsの完全な環境(モデル、データベースなど)を読み込んで、対話型のIRBスタイルのシェルが起動します。Railsコンソールは、Ruby on Railsフレームワークの強力な機能であり、コマンドラインでアプリケーション全体を対話的に操作して、デバッグや調査を行えます。
Railsコンソールは、コードをプロトタイピングしてアイデアを試したり、ブラウザを使わずにデータベース内のレコードを作成・更新するのに便利です。
$ bin/rails console
my-app(dev):001:0> Post.create(title: 'First!')
Railsコンソールには、さまざまな便利機能が備わっています。
たとえば、データを変更せずにコードを試したい場合は、bin/rails console --sandboxでsandboxモードを利用できます。sandboxモードでは、すべてのデータベース操作がトランザクションでラップされ、コンソールを終了するとロールバックします。
$ bin/rails console --sandbox
Loading development environment in sandbox (Rails 8.1.0)
Any modifications you make will be rolled back on exit
my-app(dev):001:0>
sandboxオプションは、データベースに影響を与えずに破壊的な変更を安全にテストしたい場合に最適です。
-eオプションを使って、consoleコマンドのRails環境を指定することも可能です。
$ bin/rails console -e test
Loading test environment (Rails 8.1.0)
Railsコンソールでは、appとhelperのインスタンスにアクセスできます。
appメソッドを使うと、以下のように名前付きルーティングヘルパーにアクセスできます。
my-app(dev)> app.root_path
=> "/"
my-app(dev)> app.edit_user_path
=> "profile/edit"
appオブジェクトを使うと、実際のサーバーを起動せずにアプリケーションにリクエストを送信することも可能です。
my-app(dev)> app.get "/", headers: { "Host" => "localhost" }
Started GET "/" for 127.0.0.1 at 2025-08-11 11:11:34 -0500
...
my-app(dev)> app.response.status
=> 200
app.getメソッドでは、第2引数にヘッダーを渡す必要があります("Host"が無指定の場合はRackクライアントがデフォルトで"www.example.com"を使うため)。アプリケーションを変更して、常にlocalhostを使うように設定やイニシャライザで指定することも可能です。
上述したような「リクエスト送信」が可能な理由は、appオブジェクトがRailsが統合テストで使うものと同じだからです。
my-app(dev)> app.class
=> ActionDispatch::Integration::Session
appオブジェクトは、app.cookies、app.session、app.post、およびapp.responseなどのメソッドを公開しています。このようにして、Railsコンソールで統合テストをシミュレートしてデバッグできます。
helperオブジェクトは、RailsコンソールにおけるRailsのビュー層への直接的な入口です。このオブジェクトを使えば、コンソール内でビュー関連のフォーマットやユーティリティメソッドをテストすることも、アプリケーション内で定義されたカスタムヘルパー(app/helpers内)を利用することも可能になります。
my-app(dev)> helper.time_ago_in_words 3.days.ago
=> "3 days"
my-app(dev)> helper.l(Date.today)
=> "2025-08-11"
my-app(dev)> helper.pluralize(3, "child")
=> "3 children"
my-app(dev)> helper.truncate("This is a very long sentence", length: 22)
=> "This is a very long..."
my-app(dev)> helper.link_to("Home", "/")
=> "<a href=\"/\">Home</a>"
custom_helperメソッドがapp/helpers/*_helper.rbファイル内で定義されていれば、以下のように利用できます。
my-app(dev)> helper.custom_helper
"testing custom_helper"
bin/rails dbconsoleコマンドを実行すると、利用中のデータベースの種類を自動的に識別して、そのデータベースに適したコマンドラインインターフェースに接続します。また、config/database.ymlファイルと現在のRails環境に基づいて、セッションを開始するためのコマンドラインパラメータも自動的に設定されます。
dbconsoleセッションに入ると、通常の方法でデータベースと直接対話できます。たとえば、PostgreSQLを利用している場合、bin/rails dbconsoleを実行すると次のようになります。
$ bin/rails dbconsole
psql (17.5 (Homebrew))
Type "help" for help.
booknotes_development=# help
You are using psql, the command-line interface to PostgreSQL.
Type: \copyright for distribution terms
\h for help with SQL commands
\? for help with psql commands
\g or terminate with semicolon to execute query
\q to quit
booknotes_development=# \dt
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
--------+--------------------------------+-------+-------
public | action_text_rich_texts | table | bhumi
...
dbconsoleコマンドは、個別のデータベースコマンドを実行するよりもずっと便利です。このコマンドは、database.ymlファイルに基づく適切な引数を手動で指定してpsql(またはmysqlやsqlite)コマンドを実行するのと同等です。
psql -h <host> -p <port> -U <username> <database_name>
database.ymlファイルで以下のようにPostgreSQLデータベースが設定されているとします。
development:
adapter: postgresql
database: myapp_development
username: myuser
password:
host: localhost
この場合、bin/rails dbconsoleコマンドを実行することは、以下を実行するのと同等です。
psql -h localhost -U myuser myapp_development
dbconsoleコマンドでサポートされているのは、MySQL(MariaDBを含む)、PostgreSQL、およびSQLite3です。dbconsoleのエイリアスとして"db"も利用できます(bin/rails db)。
複数のデータベースを利用している場合、bin/rails dbconsoleはデフォルトでprimaryデータベースに接続します。接続するデータベースを指定するには、--database(または--db)オプションを使います。
$ bin/rails dbconsole --database=animals
bin/rails runnerコマンドを使うと、bin/rails consoleを必要とせずに、RubyのコードをRailsのコンテキストで非対話的に実行できます。このコマンドは、Railsコンソールで対話操作を行う必要のない、1回きりのタスクを実行するのに便利です。たとえば以下のように実行できます。
$ bin/rails runner "puts User.count"
42
$ bin/rails runner 'MyJob.perform_now'
-eオプションを使うと、runnerコマンドを実行するときの環境を指定できます。
$ bin/rails runner -e production "puts User.count"
以下のように、Rubyファイル内のコードをRailsアプリケーションのコンテキストで実行することも可能です。
$ bin/rails runner lib/path_to_ruby_script.rb
bin/rails runnerで実行するスクリプトは、デフォルトではRails Executorで自動的にラップされます。Rails Executorは、Railsアプリケーションに関連付けられたActiveSupport::Executorのインスタンスです。
Rails Executorは、Railsアプリケーション内で任意のRubyコードを実行するための「セーフゾーン」を作成し、オートローダー、ミドルウェアスタック、Active Supportフックがすべて一貫して動作するようにします。
つまり、bin/rails runner lib/long_running_scripts.rbを実行することは、機能的に以下のコードを実行するのと同等です。
Rails.application.executor.wrap do
# lib/long_running_scripts.rb内のコードをここで実行する
end
--skip-executorオプションを渡すことで、この振る舞いをスキップできます。
$ bin/rails runner --skip-executor lib/long_running_script.rb
bin/rails bootコマンドは、Railsアプリケーションを起動するための低レベルのRailsコマンドであり、Railsアプリケーションを起動することだけが目的です。具体的には、config/boot.rbおよびconfig/application.rbファイルを読み込んで、アプリケーション環境が実行可能な状態になるようにします。
bootコマンドはアプリケーションを起動して終了するだけで、他には何もしないので、起動の問題をデバッグするときに便利です。アプリケーションの起動に失敗し、マイグレーションの実行やサーバーの起動などを行わずに起動フェーズを分離したい場合は、bin/rails bootで手軽にテストできます。
bootコマンドは、アプリケーションの初期化のタイミングを調査するのにも便利です。bin/rails bootをプロファイラでラップすることで、アプリケーションの起動に要する時間をプロファイリングできます。
bin/rails routesコマンドは、アプリケーションで定義されているすべてのルーティングを一覧表示します。URIパターンやHTTP verb、対応するコントローラアクションも表示されます。
$ bin/rails routes
Prefix Verb URI Pattern Controller#Action
books GET /books(:format) books#index
books POST /books(:format) books#create
...
...
このコマンドは、ルーティングの問題を追跡したり、Railsアプリケーションのリソースとルートの概要を把握したりするのに役立ちます。routesコマンドの出力を--controller(-c)や--grep(-g)などのオプションで絞り込むことも可能です。
# 名前に"users"を含むコントローラのルーティングだけを表示する
$ bin/rails routes --controller users
# Admin::UsersController名前空間で処理されるルーティングだけを表示する
$ bin/rails routes -c admin/users
# -g(または--grep)で名前、パス、またはコントローラ/アクションで検索する
$ bin/rails routes -g users
bin/rails routes --expandedオプションを使うと、個別のルーティング情報がさらに詳しく表示されます。たとえば、ルーティングがconfig/routes.rbファイルのどの行で定義されているかも確認できます。
$ bin/rails routes --expanded
--[ Route 1 ]--------------------------------------------------------------------------------
Prefix |
Verb |
URI | /assets
Controller#Action | Propshaft::Server
Source Location | propshaft (1.2.1) lib/propshaft/railtie.rb:49
--[ Route 2 ]--------------------------------------------------------------------------------
Prefix | about
Verb | GET
URI | /about(.:format)
Controller#Action | posts#about
Source Location | /Users/bhumi/Code/try_markdown/config/routes.rb:2
--[ Route 3 ]--------------------------------------------------------------------------------
Prefix | posts
Verb | GET
URI | /posts(.:format)
Controller#Action | posts#index
Source Location | /Users/bhumi/Code/try_markdown/config/routes.rb:4
developmentモードでは、ブラウザでhttp://localhost:3000/rails/info/routesにアクセスすることでも同じルーティング情報を確認できます。
bin/rails aboutを実行すると、Ruby、RubyGems、Rails、Railsのサブコンポーネントのバージョン、Railsアプリケーションのフォルダー名、現在のRailsの環境名とデータベースアダプタ、スキーマのバージョンが表示されます。
チーム内やフォーラムで質問するときや、セキュリティパッチが自分のアプリケーションに影響するかどうかを確認したいときなど、現在使っているRailsに関する情報が必要なときに便利です。
$ bin/rails about
About your application's environment
Rails version 8.1.0
Ruby version 3.2.0 (x86_64-linux)
RubyGems version 3.3.7
Rack version 3.0.8
JavaScript Runtime Node.js (V8)
Middleware: ActionDispatch::HostAuthorization, Rack::Sendfile, ...
Application root /home/code/my_app
Environment development
Database adapter sqlite3
Database schema version 20250205173523
bin/rails initializersコマンドは、Railsで定義されているすべてのイニシャライザを、Railsが呼び出す順序で出力します。
$ bin/rails initializers
ActiveSupport::Railtie.active_support.deprecator
ActionDispatch::Railtie.action_dispatch.deprecator
ActiveModel::Railtie.active_model.deprecator
...
Booknotes::Application.set_routes_reloader_hook
Booknotes::Application.set_clear_dependencies_hook
Booknotes::Application.enable_yjit
このコマンドは、イニシャライザ同士の依存関係が存在していて、実行順序が重要な場合に便利です。イニシャライザの前後でどんなイニシャライザが実行されるかをこのコマンドで確認し、イニシャライザ間の関係を把握できます。Railsは、最初にフレームワークのイニシャライザを実行し、その後にconfig/initializers/ディレクトリで定義されたアプリケーションのイニシャライザを実行します。
bin/rails middlewareコマンドは、Railsアプリケーションの全Rackミドルウェアスタックを、各リクエストに対してミドルウェアが実行される正確な順序で表示します。
$ bin/rails middleware
use ActionDispatch::HostAuthorization
use Rack::Sendfile
use ActionDispatch::Static
use ActionDispatch::Executor
use ActionDispatch::ServerTiming
...
このコマンドは、Railsアプリケーションのミドルウェアスタックを確認して、どれがgemによって追加されたかを把握したり(例: Devise gemで追加されるWarden::Manager)、デバッグやプロファイリングを行ったりするのに便利です。
bin/rails statsコマンドは、アプリケーション内のさまざまなコンポーネントのコード行数(LOC)やクラス数、メソッド数などを表示します。
$ bin/rails stats
+----------------------+--------+--------+---------+---------+-----+-------+
| Name | Lines | LOC | Classes | Methods | M/C | LOC/M |
+----------------------+--------+--------+---------+---------+-----+-------+
| Controllers | 309 | 247 | 7 | 37 | 5 | 4 |
| Helpers | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jobs | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Models | 89 | 70 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| Mailers | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Channels | 16 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Views | 622 | 501 | 0 | 1 | 0 | 499 |
| Stylesheets | 584 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JavaScript | 81 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libraries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Controller tests | 117 | 75 | 4 | 9 | 2 | 6 |
| Helper tests | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Model tests | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mailer tests | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Integration tests | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| System tests | 51 | 41 | 1 | 4 | 4 | 8 |
+----------------------+--------+--------+---------+---------+-----+-------+
| Total | 1924 | 1541 | 26 | 58 | 2 | 24 |
+----------------------+--------+--------+---------+---------+-----+-------+
Code LOC: 1411 Test LOC: 130 Code to Test Ratio: 1:0.1
bin/rails time:zones:allコマンドは、Active Supportが認識しているすべてのタイムゾーンの完全なリストを、UTCオフセットとRailsのタイムゾーン識別子とともに表示します。
たとえば、bin/rails time:zones:localコマンドを使うと、システムのタイムゾーンを確認できます。
$ bin/rails time:zones:local
* UTC -06:00 *
Central America
Central Time (US & Canada)
Chihuahua
Guadalajara
Mexico City
Monterrey
Saskatchewan
このコマンドは、config/application.rbでconfig.time_zoneを設定するときに、正確なRailsのタイムゾーン名とスペル(例: "Pacific Time (US & Canada)")が必要な場合や、ユーザー入力のバリデーションやデバッグ時に役立ちます。
bin/rails assets:*コマンドを使って、app/assets/ディレクトリ内のアセットを管理できます。
assets:名前空間に属する利用可能なすべてのコマンドの一覧は、以下のように表示できます。
$ bin/rails -T assets
bin/rails assets:clean[count] # Removes old files in config.assets.output_path
bin/rails assets:clobber # Remove config.assets.output_path
bin/rails assets:precompile # Compile all the assets from config.assets.paths
bin/rails assets:reveal # Print all the assets available in config.assets.paths
bin/rails assets:reveal:full # Print the full path of assets available in config.assets.paths
bin/rails assets:precompileコマンドを使ってapp/assets/ディレクトリ内のアセットをプリコンパイルできます。プリコンパイルについて詳しくは、アセットパイプラインガイドを参照してください。
bin/rails assets:cleanコマンドを使って、古いコンパイル済みアセットを削除できます。assets:cleanコマンドは、新しいアセットがビルドされている間にまだ古いアセットにリンクしている可能性のある状態でのローリングデプロイが可能になります。
public/assets/ディレクトリ内のアセットを完全に削除したい場合は、bin/rails assets:clobberコマンドを使えます。
このセクションのコマンドであるbin/rails db:*は、すべてデータベースのセットアップやマイグレーションの管理などに関するものです。
以下のようにdb:名前空間を指定すると、db:*のすべてのコマンドの一覧を表示できます。
$ bin/rails -T db
bin/rails db:create # Create the database from DATABASE_URL or
bin/rails db:drop # Drop the database from DATABASE_URL or
bin/rails db:encryption:init # Generate a set of keys for configuring
bin/rails db:environment:set # Set the environment value for the database
bin/rails db:fixtures:load # Load fixtures into the current environments
bin/rails db:migrate # Migrate the database (options: VERSION=x,
bin/rails db:migrate:down # Run the "down" for a given migration VERSION
bin/rails db:migrate:redo # Roll back the database one migration and
bin/rails db:migrate:status # Display status of migrations
bin/rails db:migrate:up # Run the "up" for a given migration VERSION
bin/rails db:prepare # Run setup if database does not exist, or run
bin/rails db:reset # Drop and recreate all databases from their
bin/rails db:rollback # Roll the schema back to the previous version
bin/rails db:schema:cache:clear # Clear a db/schema_cache.yml file
bin/rails db:schema:cache:dump # Create a db/schema_cache.yml file
bin/rails db:schema:dump # Create a database schema file (either db/
bin/rails db:schema:load # Load a database schema file (either db/
bin/rails db:seed # Load the seed data from db/seeds.rb
bin/rails db:seed:replant # Truncate tables of each database for current
bin/rails db:setup # Create all databases, load all schemas, and
bin/rails db:version # Retrieve the current schema version number
bin/rails test:db # Reset the database and run `bin/rails test`
db:createとdb:dropコマンドは、現在の環境のデータベースを作成または削除します(db:create:all、db:drop:allで全環境のデータベースを対象にできます)。
db:seedコマンドは、db/seeds.rbからサンプルデータを読み込みます。
db:seed:replantコマンドは、現在の環境の各データベースのテーブルの内容を空にしてからseedデータを読み込みます。
db:setupコマンドは、すべてのデータベースを作成し、すべてのスキーマを読み込み、seedデータで初期化します(次のdb:resetコマンドのように最初にデータベースを削除することはありません)。
db:resetコマンドは、現在の環境のすべてのデータベースを削除して再作成し、スキーマから読み込み、seedデータを読み込みます(上記のコマンドの組み合わせです)。
db:migrateコマンドは、Railsアプリケーションでよく使われるコマンドです。このコマンドは、すべての新しい(つまり未実行の)マイグレーションを実行することで、データベースをマイグレーションします。
db:migrate:upコマンドを実行すると、VERSION引数で指定したマイグレーションのupメソッドを実行します。
db:migrate:downコマンドを実行すると、同様にdownメソッドを実行します。
$ bin/rails db:migrate:down VERSION=20250812120000
db:rollbackコマンドは、スキーマを直前のバージョンにロールバックします(STEP=n引数でステップ数を指定することも可能です)。
db:migrate:redoコマンドは、データベースをマイグレーション1つ分ロールバックしてから、再度マイグレーションを実行します。これは、上記の2つのコマンドの組み合わせです。
db:migrate:statusコマンドも利用できます。これは、どのマイグレーションが実行済みで、どのマイグレーションが保留中であるかを表示します。
$ bin/rails db:migrate:status
database: db/development.sqlite3
Status Migration ID Migration Name
--------------------------------------------------
up 20250101010101 Create users
up 20250102020202 Add email to users
down 20250812120000 Add age to users
Railsアプリケーションのデータベーススキーマを管理するための主なコマンドは、db:schema:dumpとdb:schema:loadの2つです。
db:schema:dumpコマンドは、データベースの現在のスキーマを読み取り、db/schema.rbファイル(スキーマ形式をsqlに設定している場合はdb/structure.sql)に書き出します。マイグレーションを実行した後、Railsは自動的にsсhema:dumpを呼び出すため、スキーマファイルは常に最新の状態に保たれます(手動で変更する必要はありません)。
このスキーマファイルは、データベースの設計図であり、テストや開発のための新しい環境をセットアップするのに役立ちます。スキーマはバージョン管理されているため、時間の経過に伴うスキーマの変更を確認できます。
db:schema:loadコマンドは、db/schema.rb(またはdb/structure.sql)のデータベーススキーマを削除して再作成します。これは、各マイグレーションを1つずつ再実行せずに、直接行われます。
このコマンドは、長年に渡る多数のマイグレーションを1つずつ実行せずに、データベースを現在のスキーマに短時間でリセットしたいときに便利です。たとえば、db:setupコマンドを実行すると、データベースを作成した後、シードデータを読み込む前にdb:schema:loadコマンドも呼び出されます。
db:schema:dumpはschema.rbファイルを書き込むコマンドであり、db:schema:loadはそのファイルを読み込むコマンドだと考えるとよいでしょう。
bin/rails db:versionコマンドは、データベースの現在のバージョンを表示します。トラブルシューティングで便利です。
$ bin/rails db:version
database: storage/development.sqlite3
Current version: 20250806173936
db:fixtures:loadコマンドは、フィクスチャを現在の環境のデータベースに読み込みます。特定のフィクスチャを読み込むには、FIXTURES=x,yを指定します。test/fixtures/内のサブディレクトリから読み込むには、FIXTURES_DIR=zを指定します。
$ bin/rails db:fixtures:load
-> Loading fixtures from test/fixtures/users.yml
-> Loading fixtures from test/fixtures/books.yml
db:system:changeコマンドは、config/database.ymlファイルとデータベースgemを指定のデータベースに変更できます。これにより、既存のアプリケーションでデータベースを切り替えられるようになります。
$ bin/rails db:system:change --to=postgresql
conflict config/database.yml
Overwrite config/database.yml? (enter "h" for help) [Ynaqdhm] Y
force config/database.yml
gsub Gemfile
gsub Gemfile
...
db:encryption:initコマンドは、指定の環境でActive Record暗号化を設定するためのキーセットを生成します。
bin/rails testコマンドは、アプリケーション内のさまざまな種類のテストを実行できます。
bin/rails test --helpを実行すると、このコマンドのさまざまなオプションの良い例を参照できます。
以下のようにファイル名と行番号を指定して、特定のテストを実行できます。
bin/rails test test/models/user_test.rb:27
行番号の範囲を指定して複数のテストを実行することも可能です。
bin/rails test test/models/user_test.rb:10-20
テストファイルやディレクトリを同時に複数指定することも可能です。
bin/rails test test/controllers test/integration/login_test.rb
RailsにはMinitestというテストフレームワークが付属しており、testコマンドで利用できるMinitestオプションもあります。
# /validation/という正規表現にマッチする名前のテストだけを実行する
$ bin/rails test -n /validation/
Railsで実行できるテストの種類や解説については、テスティングガイドを参照してください。
bin/rails notesは、特定のキーワードで始まるコードコメントを検索して表示します。bin/rails notes --helpで利用法を表示できます。
デフォルトでは、app、config、db、lib、testディレクトリにある、拡張子が.builder、.rb、.rake、.yml、.yaml、.ruby、.css、.js、.erbのファイルの中から、「FIXME」「OPTIMIZE」「TODO」キーワードで始まるコメントを検索します(訳注: コメントのキーワードが[FIXME]のように[]で囲まれていると検索されません)。
$ bin/rails notes
app/controllers/admin/users_controller.rb:
* [ 20] [TODO] any other way to do this?
* [132] [FIXME] high priority for next deploy
lib/school.rb:
* [ 13] [OPTIMIZE] refactor this code to make it faster
--annotations(または-a)引数で特定のアノテーションを指定できます。アノテーションは大文字小文字を区別する点にご注意ください。
$ bin/rails notes --annotations FIXME RELEASE
app/controllers/admin/users_controller.rb:
* [101] [RELEASE] We need to look at this before next release
* [132] [FIXME] high priority for next deploy
lib/school.rb:
* [ 17] [FIXME]
config.annotations.register_tags設定でデフォルトのタグを追加できます。
config.annotations.register_tags("DEPRECATEME", "TESTME")
$ bin/rails notes
app/controllers/admin/users_controller.rb:
* [ 20] [TODO] do A/B testing on this
* [ 42] [TESTME] this needs more functional tests
* [132] [DEPRECATEME] ensure this method is deprecated in next release
config.annotations.register_directories設定でデフォルトのディレクトリを追加できます。
config.annotations.register_directories("spec", "vendor")
config.annotations.register_extensions設定でデフォルトのファイル拡張子を追加できます。
config.annotations.register_extensions("scss", "sass") { |annotation| /\/\/\s*(#{annotation}):?\s*(.*)$/ }
Rails.root/tmpディレクトリには一時ファイルが保存されます(*nix系でいう/tmpディレクトリと同様です)。一時ファイルには、プロセスIDのファイル、アクションキャッシュのファイルなどがあります。
tmp:名前空間には、Rails.root/tmpディレクトリを作成・削除する以下のタスクがあります。
$ bin/rails tmp:cache:clear # `tmp/cache`をクリアする
$ bin/rails tmp:sockets:clear # `tmp/sockets`をクリアする
$ bin/rails tmp:screenshots:clear # `tmp/screenshots`をクリアする
$ bin/rails tmp:clear # すべてのキャッシュ、ソケット、スクリーンショットをクリアする
$ bin/rails tmp:create # キャッシュ、ソケット、PID用の`tmp`ディレクトリを作成する
bin/rails secretコマンドは、Railsアプリケーションでシークレットキーとして使うための、暗号学的に安全なランダム文字列を生成します。
$ bin/rails secret
4d39f92a661b5afea8c201b0b5d797cdd3dcf8ae41a875add6ca51489b1fbbf2852a666660d32c0a09f8df863b71073ccbf7f6534162b0a690c45fd278620a63
このコマンドは、アプリケーションのconfig/credentials.yml.encファイルにシークレットキーを設定する場合に便利です。
bin/rails credentialsコマンドは、暗号化されたcredential(資格情報)へのアクセスを提供します。これにより、アクセストークンやデータベースのパスワードなどをアプリ内に安全に保存でき、多数の環境変数に依存する必要がなくなります。
暗号化されたYMLファイルconfig/credentials.yml.encに値を追加するには、credentials:editコマンドを実行します。
$ bin/rails credentials:edit
実行すると、復号したcredentialファイルがエディタで開かれます(エディタは$VISUALまたは$EDITORで設定します)。変更を保存すると、ファイルの内容は自動的に暗号化されます。
:showコマンドを使って、復号したcredentialファイルを表示することも可能です。表示内容は以下のようになります(これはサンプルアプリケーションのものであり、機密データではありません)。
$ bin/rails credentials:show
# aws:
# access_key_id: 123
# secret_access_key: 345
active_record_encryption:
primary_key: 99eYu7ZO0JEwXUcpxmja5PnoRJMaazVZ
deterministic_key: lGRKzINTrMTDSuuOIr6r5kdq2sH6S6Ii
key_derivation_salt: aoOUutSgvw788fvO3z0hSgv0Bwrm76P0
# Used as the base secret for all MessageVerifiers in Rails, including the one protecting cookies.
secret_key_base: 6013280bda2fcbdbeda1732859df557a067ac81c423855aedba057f7a9b14161442d9cadfc7e48109c79143c5948de848ab5909ee54d04c34f572153466fc589
credentialsについて詳しくは、Railsセキュリティガイドを参照してください。
このコマンドの詳しい説明は、bin/rails credentials --helpで参照できます。
アプリケーションで独自のrakeタスクを作成したい場合があります(古いレコードをデータベースから削除するなど)。これは、bin/rails generate taskコマンドで行えます。
カスタムrakeタスクファイルの拡張子は.rakeで、Railsアプリケーションのlib/tasks/フォルダに配置されます。
たとえば以下のようにコマンドを実行します。
$ bin/rails generate task cool
create lib/tasks/cool.rake
このcool.rakeファイルで、以下のようにタスクを定義できます。
desc "手短でクールなタスクの概要"
task task_name: [:prerequisite_task, :another_task_we_depend_on] do
# 任意の有効なRubyコードを書ける
end
カスタムrakeタスクに引数を渡せるようにするには、以下のようにします。
task :task_name, [:arg_1] => [:prerequisite_1, :prerequisite_2] do |task, args|
argument_1 = args.arg_1
end
タスクを名前空間内で定義することで、タスクをグループ化できます。
namespace :db do
desc "データベース関連の作業を行うタスク"
task :my_db_task do
# ...
end
end
タスクの呼び出しは以下のように行います。
$ bin/rails task_name
$ bin/rails "task_name[value 1]" # 引数の文字列全体を引用符で囲むこと
$ bin/rails "task_name[value 1, value2, value3]" # 複数の引数はカンマで区切る
$ bin/rails db:nothing
アプリケーションモデルの操作やデータベースクエリの実行などが必要なタスクは、以下のようにenvironmentタスクを使ってRailsアプリケーションを読み込めます。
task task_that_requires_app_code: [:environment] do
puts User.count
end
🖋 GitHubで編集を提案する
/
📕 英語で読む
Railsガイドは GitHub の yasslab/railsguides.jp で管理・公開されております。本ガイドを読んで気になる文章や間違ったコードを見かけたら、気軽に Pull Request を出して頂けると嬉しいです。Pull Request の送り方については GitHub の README をご参照ください。
原著における間違いを見つけたら『Rails のドキュメントに貢献する』を参考にしながらぜひ Rails コミュニティに貢献してみてください 🛠💨✨
本ガイドの品質向上に向けて、皆さまのご協力が得られれば嬉しいです。
Railsガイド運営チーム (@RailsGuidesJP)

Railsガイドは下記の協賛企業から継続的な支援を受けています。もしご興味あれば、協賛プランから気軽にお問い合わせいただけると嬉しいです。
- Star
-

-